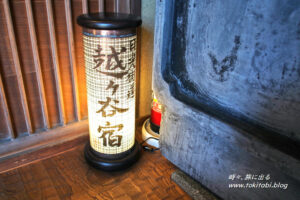西福寺は、平安時代に弘法大師が国家鎮護のため創建したと伝わる古刹です。
その境内には、徳川3代将軍・家光の長女・千代姫が奉納したと伝わる三重塔が残っています。
江戸時代の三重塔は県内では3ヶ所にしか現存しておらず、これはその内の一つとして貴重なんですよ。
江戸時代には百観音の参拝地として賑わった歴史なども交えながら、西福寺の見どころを紹介します。
目次
西福寺には江戸時代の貴重な三重塔が残る
弘法大師が創建したと伝わる古刹


西福寺は住宅地からは少し外れた場所にあり、緑に囲まれた、少し里山のような雰囲気の中にありました。
正面には門もなく、入口からは観音堂へと真っすぐ続く参道が見えます。
西福寺は真言宗の寺院で、平安時代の弘仁年間(810~824年)に弘法大師が国家鎮護のために創建した、と伝わる古刹です。
江戸時代には、江戸の増上寺の末寺という位置付けになっているようですね。


入口両脇を固めている金剛力士像。


けっこう本格的に凄みのある金剛力士像だなあ、と思いつつ脇を抜けて境内へ。
県内に残る江戸時代の三重塔は三か所のみ


境内に入る前から既に見えているのが、本日のお目当ての一つであるこちらの三重塔。なかなか立派な塔ですね!
埼玉県内で江戸時代の三重塔の塔が残っているのは、実はわずか三か所だけなんですね。行田市にある成就院、吉見町にある安楽寺、そしてこの西福寺です。
その中で最も古いのが寛永期(1624~1644年)に建立された安楽寺の塔で、元禄6年(1693年)建立の西福寺の三重塔はそれに次ぐ古いものとなります。
\ 安楽寺の詳細についてはこちら!/
三重塔は徳川家光の長女・千代姫が建立


この三重塔は徳川3代将軍・家光の長女である千代姫が願主となって建立された、と伝わるものです。
千代姫(1637-1699年)
江戸幕府第3代将軍・徳川家光の待望の第一子で、母は側室のお振の方(宝樹院)。
幼少より聡明とされ、慶安3年(1650年)に尾張徳川家2代藩主・徳川光友に2歳6カ月の時点で嫁ぎ、尾張藩の御姫様としての生活を送ります。
この婚姻により幕府と尾張徳川家の結びつきが強化され、千代姫は政治的にも重要な役割を果たしました。
千代姫婚礼の際の調度品は芸術性が高いとされ、国宝指定されていることでも知られます。
2歳で嫁入りですかあ。う~む、凄い時代ですなあ。
塔内には釈迦三尊のほか、千代姫の位牌も安置されているとのことです。
西福寺と千代姫の繋がりについてですが、西福寺は徳川家の菩提寺である増上寺の末寺であった、という間接的な繋がりはあるものの、直接的な結びつきについては調べても分かりませんでした。


三重塔は盛土した基礎の上に敷いた、自然石を礎石として建っています。
構造的には一層の天井から真上に一本の柱を建て、その柱から二層・三層の屋根に梁を渡す造りとのこと。
地震による崩壊も無かったことから、これで絶妙なバランスが取られているんでしょうねえ。
さらに組材には鉄製の釘を使用せず、すべて木の組細工で組上がっているのも注目すべき点です。
様式は方三間(ほうさんけん)と呼ばれもので、四方どこから見ても4本の柱とその間の間が3つある形状となっています。


一層の天井近くには、荷重を分散させるための蟇股(かえるまた)と呼ばれる部材が付いていますが、ここに方角を現す十二支の動物の彫刻が施されています。
こちらの猿は南西の方角を示すもの。


方角と十二支の動物が結び付けられるのは、陰陽道や風水の影響とされます。
良く耳にする鬼門(北東)や裏鬼門(南西)など、特定の方角からは災いが入りやすいといわれますよね。そして、そこに対応する動物を置くと悪霊・災厄を防ぐ、ともいわれていました。
江戸時代は百観音参拝者で賑わった


再び境内を進むと、西福寺の中心的な建物となる観音堂があります。
現在の観音堂は元禄3年(1690年)に再興されたものとのことなので、結構古い建築物ですね。


観音堂には高さ90㎝・幅55㎝の如意輪観音坐像が、御本尊として納められています。
その御本尊の胎内には西国・坂東・秩父の札所の小観音像があわせて99体納められており、本尊を入れて百観音となるそうだ。
ちなみに御本尊の両脇には、後世に作られた99体の観音像がさらに並んでいるとのこと。


百観音を納めるこの一堂の参詣で百ヵ所の札所めぐりと同じ御利益が頂ける、とのことで、江戸時代には江戸からの参拝者で大変にぎわったそうなんですね。

 観音堂脇にある常念観音菩薩像
観音堂脇にある常念観音菩薩像
江戸から川口宿までの距離は13km程度で、そこから西福寺まで足を延ばしても日帰りの圏内。
江戸から近い割には山里の風情が残っている西福寺周辺は、江戸庶民にとって信仰と小旅行を兼ねた手頃な行楽地だったようです。

 百観音供養塔
百観音供養塔
この地は江戸の文人をも惹きつけ、「遊歴雑記」の著者・津田大浄(つだ だいじょう)もこの地で百観音に参詣し、野点(のだて = 野外の茶会のこと)や連句を楽しんでいます。
ちなみに江戸時代の話かは分かりませんでしたが、かつては三重塔に櫓を組んで塔の頂上まで参詣者に登らせた時代もあった、との説明もありました。
現在では信じがたいですが(苦笑)、賑わっていた様子が目に浮かんできました。
遊歴雑記とは
江戸時代後期の僧・津田大浄が著した地誌・随筆で、各地を巡った見聞を詳細に記した著作です。
大浄は真言宗の僧侶で、修行と遊歴を兼ねて諸国を訪ね、地理・伝承・寺社縁起・人物逸話などを克明に書き留めました。
その記録は地方史や文化史の貴重な資料として評価され、特に関東・東北地方の風俗や信仰の様子を伝える点に特色があります。江戸時代の民間の生活文化を知る、貴重な手がかりとなっています。
地蔵堂に延命地蔵と閻魔大王が揃い踏み


こちらは観音堂の正面左手にある地蔵堂。


覗かせて頂いたら、中央には延命地蔵菩薩像、その右手に閻魔(えんま)大王像、左手が奪衣婆(だつえば)像が収められていました。
奪衣婆は三途の川で亡者の衣服を剥ぎ取る、といわれる老婆の鬼ですね。怖っ!
地獄の主とされる閻魔大王と、それを救う延命地蔵菩薩。対照的な両者ですが、実は一心同体であるという説もあるそうですよ。
なぜか増上寺にある西福寺の仁王像


西福寺の参拝については以上ですが、関連情報として東京都港区芝にある増上寺の仁王像を最後に紹介します。
増上寺は徳川将軍家の菩提寺として良く知られており、千代姫も62歳で亡くなった後、霊仙院の法名で増上寺に葬られています。
写真は増上寺に残っている、徳川秀忠の霊廟(墓所)の門である「旧台徳院霊廟惣門(きゅうだいとくいんれいびょうそうもん)」です。


この門に納められている仁王像が、実は元々は西福寺の仁王門に安置されていたものだというんですね。
旧台徳院霊廟惣門へは、昭和33年(1958年)頃に安置されています。
かつての西福寺には仁王門があったようですね。


像の体内から発見された修理銘札により、西福寺で寛政元年(1789年)と弘化3年(1847年)の2度修理されていることがわかっています。
さらに、安政2年(1855年)の暴風で破損したまま観音堂の片隅に置かれていたものを、昭和23年(1948年)に三重塔の修理と同時期に3度目の修理を実施。
その後、東京浅草寺に移されたことまで記載されていたそうだ。その後の経緯については不詳とのこと。
ちょっとミステリアスな経路をたどった、西福寺の仁王像の話でした。
\ 増上寺の詳しい記事についてはこちら!/
坂東三十三観音と他の寺をあわせた、関東の百寺を紹介。
「地球の歩き方シリーズ」なのでしっかりした内容!
絶景本は数々あれど、埼玉にしぼられているのが良い。
一年中楽しめる、埼玉の花の名所と里山の風景の紹介。
西福寺の詳細情報とアクセス
西福寺
住所:埼玉県川口市西立野420(GoogleMapで開く)
アクセス:
電車)
・埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」から徒歩約10分
車)
・東京外環自動車道「川口東IC」から約1km
・駐車場有り
川口のランチは事前予約やクーポン利用で、並ばずお得に!!
西福寺へ参拝に出かけませんか?
江戸時代の三重塔が現存する古刹・西福寺は、歴史を感じさせる貴重なスポットでした。
この近隣には江戸時代に関東郡代として活躍した伊奈家の陣屋跡である赤山陣屋跡などもあるので、そちらと併せて訪問すると歴史好きはさらに楽しめると思いますよ。
西福寺に出かけてみませんか?
記事の訪問日:2022/9/25





 川口市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!
川口市周辺の立寄りスポットを探して予約しよう!割引プランも!
近隣スポットもチェック!
あわせて読みたい
赤山陣屋跡、空堀が多く残る関東郡代・伊奈忠治の屋敷跡【埼玉・川口市】
赤山陣屋(赤山城)跡は、利根川を江戸に直接流れぬようにした利根川東遷事業など、大掛かりな治水工事で江戸の発展に貢献した伊奈氏の屋敷跡です。屋敷を囲んでいた空…
あわせて読みたい
川口九社詣 勾玉巡り、専用御朱印帳を片手に楽しく運気アップ!【埼玉・川口市】
埼玉県川口市には多くの神社がありますが、その代表となる神社が川口九社です。勾玉の形を描くようにその九社を巡拝するのが「川口九社詣 勾玉巡り」。いずれも地元の鎮…
あわせて読みたい
旧田中家住宅、大正時代の本格洋館に隠れる和洋折衷の魅力【埼玉・川口市】
関東近郊で本格な洋館建築を見学したいとなると、思いつく場所は横浜あたりでしょうか?でも実は、埼玉県の川口市でも本格な洋館の見学ができますよ!「旧田中家住宅」…
あわせて読みたい
日光街道 越ヶ谷宿、今も古い建物が多く残るかつて舟運で栄えた宿【埼玉・越谷市】
日光街道の宿場町としては千住宿に次ぐ規模を誇った「越ヶ谷宿」は、街道と河川が交わる交通の要所にあったため、舟運による物資の集積所として発達していた。そんな宿…
さらに「埼玉県」に関する記事を探す


埼玉県内の古刹をさらにチェック!
あわせて読みたい
源範頼ゆかりの吉見観音 安楽寺、県内最古の三重塔は必見!【埼玉・吉見町】
奈良時代が起源とされ千二百年の歴史を持つ古刹「岩殿山 安楽寺」は、源頼朝の異母弟である源範頼がかつて幼少期に身を隠したと伝わる寺院です。また、その後に吉見に館…
あわせて読みたい
岩殿観音正法寺、比企能員が北条政子の守り本尊を祀った古刹【埼玉・東松山市】
埼玉県東松山市にある「岩殿観音 正法寺」は森に囲まれた丘陵地に佇んでおり、山寺のような雰囲気を持っている古刹です。坂東三十三所観音霊場の10番霊場に数えられる正…
あわせて読みたい
「龍穏寺」太田道灌の生誕地で、道灌の墓所がある古刹を訪ねる【埼玉・越生町】
室町時代後期に関東で活躍した武将・太田道灌は、江戸城を築くなどで築城名人といわれた一方、歌にも通じたことから文武両道を実践した名将として知られています。そん…
あわせて読みたい
息障院、源頼朝の弟・源範頼の館跡で数奇なその生涯に触れる【埼玉・吉見町】
埼玉県吉見町にある古刹・息障院がある場所には、鎌倉時代、源頼朝の異母弟だった源範頼の屋敷があったと伝わります。現在の「御所」という地名も、一帯が「吉見御所」…
<a href=”//ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3694017&pid=890454465″ rel=”nofollow noopener” target=”_blank”><img src=”//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3694017&pid=890454465″ border=”0″></a>
クラブツーリズムはバスツアーやテーマ旅行が充実!